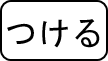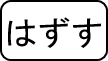令和7年度 第5回 本宿小開かれた学校づくり協議会
令和7年度 第5回 本宿小開かれた学校づくり協議会
月曜朝の学級の時間について
11月1日 14:30~16:00
前半は、はとの子作品展を鑑賞し、作品展の感想や開催までの児童の様子などの情報交換を行いました。
後半は地域の情報を集めて試作した地域の年間活動カレンダーのサンプルをたたき台とした協議と、学校評価アンケートの項目についての説明がありました。
1.はとの子作品展鑑賞
栗本主幹教諭に解説をしていただきながら、校内の展示をツアー形式で鑑賞しました。
児童の発達段階に応じたアプローチの解説は大変興味深く、それぞれの学年の作品がのびのびと制作されているのが印象的でした。

6年生になると人を楽しませる視点で作品作りができるとのことで、フォトスポットの作品を楽しませてもらいました。
 |
 |
委員からの感想
- 図工は子どもたちが自分を解放させることができる教科で、いろいろなものを引き出せる仕掛けが盛り込まれていることが確認できた。このような機会が子どもたちに与えられていることが本当に良いと感じた。
- 子ども学芸員の子が素晴らしかった。創作しただけでなく、それを自分の言葉で表現して人に伝えるところまでやることがすごい。突然依頼されてもやってくれて頼もしかった。
- 体育館での生演奏には卒業生も来てくれた。今回は中学生には依頼しなかったが、今後中学生が戻ってきて参加できる機会があるとよい。
学校より
- 子ども学芸員は6年生が全員担当を持って関わっている。担当の学年にインタビューに行って自分たちでまとめて発表している。上級生が下級生に関わる機会となっている。
- 動画による宣伝も、子どもたちの発想を担任が吸い上げて、考えたことを最終的に世の中に発信する体験ができた。
- 劇と作品展、これだけのものを両方毎年やるのは難しい。教室での授業がおろそかになってはいけない。3学期はふりかえりや次の学年への準備に使うため、行事を抜いた。
6年生の保護者にとっては6年生が劇がよいという意見があるが、図工で輝く子もいる。学校はいろいろな子をすくわなければいけない。
作品展はあの雰囲気があるから自己肯定感が育まれる。劇に負けない場の設定ができた。
- 持続可能にするには課題を整理する必要がある。費用面や、児童が言っていなくても先生が上をめざしてしまう場合はブレーキをかけることも必要。
2.協議事項
地域の年間活動カレンダーについて
たたき台となるサンプルを元に検討し改善点について協議しました。内容については引き続き協議する予定です。
- 大人が見て知りたい情報と子どもが参加できる情報が分かれていない
- 三中のボランティア向けの掲示がきっかけで地域でやっていることがわかるといいと情報を集めたが、年間予定が全部並んでいる情報もある。
- 全部消してしまうと、関連することに気づく機会が失われる場合もある。
- 子どもたちが市民科として武蔵野市に愛着を持って参加できるものは学校からも配信をしている。各行事の理解が進むと良い。
- お掃除大作戦などは6年生の市民科の発表で武蔵野市をより良くするために、のテーマにつなげることができた。連携ができたものには印を増やしていくのはどうか。
- 先生にも連携することで、例えば4年生の社会科で地域のお祭りという単元に盆踊りをつなげることができたり、逆に地域の方にも連携できることをわかってもらえるとよい。
- 学校の年間指導計画とうまくマッチングできるとよい。
- 〇〇日版、のように日付をつけて最新版を常にホームページで共有するようにできるとよい。
学校評価アンケート項目について
現状のアンケートの課題と改善点について、今回は主に学校側からの説明がありました。引き続き精査し、次回の第6回(11月11日)に改訂版を元に協議する予定です。
また、学校経営方針にある月曜朝の学級の時間について情報交換が行われました。
課題
- 回答率が低い。
項目を20問に絞ったことにより、いろいろな活動が混じった質問になってしまっているため、具体的ではなくなり答えにくい可能性がある。
(例:学校行事には運動会も宿泊行事もすべて入っている) - 回答している方の満足度は高いが、不満と思っている人をピックアップしたい。
改善点
- 項目を40問にして具体的に聞く。
- 教育業界の用語で保護者にわかりにくい用語の解説をつけたり、具体的な質問にする。
- 学校経営方針に対応するように項目が作られている。
- 家庭と地域の連携についても、伝わっていないとすればなぜそのような回答になるか分析したいため聞き方を工夫したい。
聞いてみたい項目のアイデアがあればいただきたい。
アンケートの方式
- 敢えて紙でとることを予定している。
デジタルだと答えやすいが、確実に回収したいものについては紙のほうがよいのではないか。 - 紙で全貌が見えるほうがよい、きょうだいで1枚ずつ答えるのもわかりやすい。
- 意図の説明・協力願い・リマインドはメールで行う。
月曜朝の学級の時間について
(学校経営方針:重点となる具体的な取り組み)
- 月曜朝15分(実質10分)、朝会をやると不登校の子にはつらいため、学級の所属感を高める時間としている
- 年間計画もなく、各学級でそれぞれ活動し、学級の状況と担任の特徴を活かす。
(例:持ち物の整理、係の時間、お話の時間、学級レクなど) - 毎週やっているので先生も学級の使い方が上手になる。
- 学級の時間があることを発信することは大事。
- 教室が楽しい場所になるようにしている。投稿しぶりが減っている。
フリースクールの出席を認める流れだが、学校としては教室に帰ることを目的としている。
不登校の子の80%はできることなら教室に帰りたいとの調査もあり、帰れる子、帰りたいと思っている子が帰って来ることができる場所は大事。
更新日:2025年11月17日 11:47:05