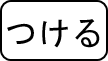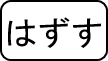令和7年度 第4回 本宿小開かれた学校づくり協議会
令和7年度 第4回 本宿小開かれた学校づくり協議会
9月11日 16:00~17:00
第4回は、前回までの内容をふまえ、今後のアクションプランに向けて熟議を行いました。
1 情報共有
まず学校より、学校の様子の報告と法律改正の説明、そして参考資料の紹介がありました。
- 2学期の状況と主要行事
- 2学期は、一部登校に課題がある児童がいるものの、全体としては概ね順調にスタート
- 今後の大きな行事としてセカンドスクールおよびプレセカンドスクールが控えており、本校は市のモデル校として、通常より1泊多い6泊7日で実施される予定
- 給特法改正について
- 「給特法(公立学校の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法)」の改正により、学校には保護者や地域住民の理解を得て業務量の管理と健康確保措置を講じることが法的に義務付け
- この目的を達成するための仕組みとして、学校の業務を以下の3つに分類
- 教師の業務だが負担を軽減するもの
(授業準備、成績処理、学校行事の準備・運営、進路指導など) - 必ずしも教師が担う必要のない業務
(例:休み時間の対応、調査回答、部活等) - 学校以外が担うべき業務
(例:登下校や放課後に関する対応、地域ボランティアとの連絡調整等)
- 教師の業務だが負担を軽減するもの
- この法改正を受け、学校としては本協議会と協力し、計画を立てて提出する
- 「スタートカリキュラム」の紹介
- 幼稚園・保育園から小学校への接続を円滑にする学校独自の取り組み
- 「キャリア教育の年間計画」の紹介
- 全学年で教科のねらいが自分のキャリア(生き方)につながっていくかを別立てて計画する資料
- 「年間指導計画」の紹介
- 各学年が年間で何を学習しているかが一覧で見られる簡易版の資料
他の委員からも夏休みの様子や地域イベントについて情報共有がありました。
- 夏休み中の子どもたちの様子
- 学校花壇の水やりの際、早朝解放に楽しそうに向かう児童を見かけた
- コミセンの事業として、大学生が中心となり、小学生を対象とした「サマースクールきゅうほ」を計画・実施。子どもたちは、ゲームやスイカ割りなどを楽しんだ。
- あそべえ
- 親が仕事をしているのは当たり前になり常連がいる
- 地域の大学生がサポート、多様な大人が関わることで、子どもたちの遊び方も変化
- 地域イベントと人材の課題:
- 盆踊りには多くの中学生が参加していた。彼らと何か連携できる可能性があるのではないかと感じた
- PTAが夏に開催した水遊び大会は多くの参加者で盛況
一方で、慢性的な人手不足が依然として大きな課題 - 第三中学校生徒会と三中開かれた学校づくり協議会メンバーとの懇談会
- 中学生から「もっとボランティアをやってみたい」という意欲的な声
- 地域側の担い手不足と結びついておらず、意欲と機会のマッチングが課題
- 地域資源の活用と連携:
- 子どもを守る家でもある「東京トヨペット」が社会貢献活動に前向き
- 児童の作品展示、社会科見学(工場見学)、吹奏楽の発表の場として店舗ロビーを提供するなど連携できる
- 子どもを守る家でもある「東京トヨペット」が社会貢献活動に前向き
- 施設の状況:
- 本宿コミュニティセンターが大規模改修工事
- 10月から翌年7月まで長期休館
- 子どもたちの居場所を確保する代替措置として「九浦の家」の児童室を平日の午後に開放予定
- 本宿コミュニティセンターが大規模改修工事
2 協議事項:地域への愛着を育む、持続可能な連携について
情報共有で明らかになった課題をもとに、議題である「子どもたちの地域への愛着をどう育むか」というテーマについて、具体的なアクションに繋げるための熟議が行われました。
2.1 年間指導計画を起点とした連携の可能性
議論の具体的な出発点として、学校から提示された「6年生の年間指導計画(簡易版)」が、地域連携の機会を具体的に見出すための有効なツールとして認識されました。
- 既に連携が実現している事例として
- 国語の授業における「古典芸能の授業(講師:青木健一氏)」
- 総合的な学習の時間における「キャリア教育(地域住民による職業講話)」
- このような学習計画が全学年分あれば、地域側が協力できる単元や時期を事前に把握しやすくなり、より計画的で効果的な連携が促進される
- かつて学校の「おどりの授業」などを通じて地域連携していた「本宿音頭」が、コロナ禍以降は途絶え、現在ではその存在を知る児童や保護者もほとんどいない状況
- 地域固有の文化を次世代へと継承していくためには、単発の学校行事としてではなく、地域の人が主体的に関わり続ける仕組みが必要
2.2 中学生ボランティアについて
「ボランティアをしたい中学生」と「人手が欲しい地域」のマッチング課題について、中学生の地域参加のあり方を巡る議論が深まりました。
- 中学生をテント設営のような単なる労働力として期待するのではなく、水遊び大会などの行事に一緒に参加し楽しんでもらう協働者としての関わりが良いのではないか
- 子どもたちを「お客様」扱いするだけでなく、本宿小や地域のために役立つ経験を通じて「自己有用感」を育む視点も不可欠であり、活動自体を楽しむ視点との両立が重要
- 中学生の積極的な参加を促すには以下の両面からアプローチする必要がある
- 「地域の一員として役立っている」と実感できる貢献の機会
- 純粋にイベントを楽しめる参加の機会
2.3 活動の「見える化」と情報集約について
「中学生がボランティアをしたくても情報がない」「地域は人手が欲しいが効果的に周知できていない」「文化継承の担い手がいない」といった課題については、地域内で行われている各団体の活動を整理・共有して「見える化」する方向で解決策を話し合いました。
- 具体的な方策として、学校の年間指導計画を見た委員から、この地域版を作成してはどうかという提案があった。これを受け、各地域団体の年間活動予定を一つに集約した「地域版の年間活動カレンダー」を作成するという案が出た
- このカレンダーの公開方法として、学校ホームページへの掲載には制約がある可能性も考慮し、まずは本協議会のウェブページ等で情報を発信し、学校ホームページからはリンクを貼るという案が検討された
3 今後のアクションプラン
協議の結果、以下の具体的な次のステップに取り組むことで合意しました。
- 各団体の年間活動計画の収集:
- 協議会メンバーが、自身が所属する各団体に対し、今後の主要な行事や活動予定(年間ベース)の提出を依頼する
- 地域活動カレンダー(地域版年間計画)の試作:
- 収集した情報を基に、地域全体の活動が見渡せるカレンダー形式の資料を試作し、協議会で共有する
- この試作は、地域活動の可視化・整理に向けた第一歩と位置づける
- 情報共有手段の検討:
- 第一中学校の廊下に地域のボランティア情報を掲示している事例なども参考にしつつ、作成したカレンダーを中学生や地域住民に効果的に周知するための最適な方法を引き続き検討する
更新日:2025年10月29日 12:06:07