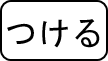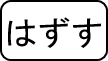令和7年度 第3回 本宿小開かれた学校づくり協議会
令和7年度 第3回 本宿小開かれた学校づくり協議会
7月17日(木)13:30~15:00
第3回は、前回までの内容をふまえ、事例の情報共有をしながら、今後に向けた方向性を探る意見交換を行いました。
当日は教育長、教育部長、指導課長もオブザーバーとして参加され、質問のご回答や補足をいただきました。
事例と現状の共有
まず、これまで地域で行われてきた活動や取り組みの事例について現状を共有しました。
- 青少協の地域行事「フレンドパーク」では、「子どもを守る家」の紹介など地域との交流が行われているが、コロナ禍以降中断している内容がある。
- あそべえでは子どもたちが自分で遊びを考え実施するお店屋さんごっこなどの企画を毎年行っている。学童では、学年に応じたルール調整をしながら集団遊びを行っている。子どもたちが楽しいと思える行事をいかに大人がサポートできるかが大事。
- 幼稚園の同窓会では76名が集まり、安心して再会できる場としてよい交流が行われた。
- 地域の盆踊りで成長した姿が見れたり、同級生の再会が実現している。
- あそべえは本宿小以外の私立・国立小学校の子も参加できるので、子ども同士を結びつけることができるとよい。
- 中高生の地域ボランティアは受験をきっかけとして参加することもあるが、きっかけとなるのであればそれでもよい。
課題と意見交換
事例を通して、地域や学校が抱える課題やそれぞれの立場から見た現状の認識を共有し、今後の方向性についての意見交換を行いました。
- PTAや青少協など、地域側の担い手が不足しており、参加のきっかけや無理のない関わり方を設計する必要がある。
- 学校・地域で重複している活動もあり、整理と情報共有によって人手不足などの課題を解消できないか。
- 「地域によって学校を変える」から「学校によって地域を変える」視点への転換があった。地域が盛り上がって、保護者も盛り上がって、常につながっていけば子どもたちがまたここに戻ってくる良いスパイラルになる。
- 三中への進学率が低いため、子どもが地元への帰属意識を持つためには本宿小が中心になる必要がある。
- 中高生の居場所づくりとして、安全管理の課題はあるものの、学校施設の活用の可能性について検討が行われた。
今後に向けた提案
今後の活動に向けて、提案やアイデアの共有が行われました。
- 地域行事の中で、子どもたちが主体となって自ら楽しめる企画を大人がサポートし、大人も巻き込んで楽しむ。
- 地域の行事・活動を整理し、保護者や地域に情報を届ける工夫を検討する。
- なるべく未就園児から大人までみんな参加できるようなものをやって人をつないでいく。
- 中高生の居場所としての学校施設の開放は、開かれた学校づくり協議会が施設利用団体を作って登録・管理をすることにより試験的に実現することは可能。もっと幅広い年代の人が集まるのもよい。
- 卒業生が自然に集える「ホームカミングデー」のような企画はどうか。
- 盆踊りで同窓生が懇親できる場を設けると参加しやすいのでは。
- 保護者や地域住民がふらっと立ち寄れる開かれた空間が作りたい。
- 学校公開の日に、地域の人と保護者が子育ての悩みなどを気軽に相談できるカフェ的なスペースを設置するのはどうか。
- ボランティア活動への参加証明書の発行を通じた中高生の関わり推進。
熟議のテーマ
今後の熟議では
1.子どもたちが「自分の地元」と感じられるような、学校を拠点とした地域活動のあり方
2.学校と地域が連携し、地域への愛着を育みながら、持続可能なつながりをどう築くか
について、開かれた学校づくり協議会として何ができるかを検討していく予定です。
更新日:2025年07月31日 16:35:26